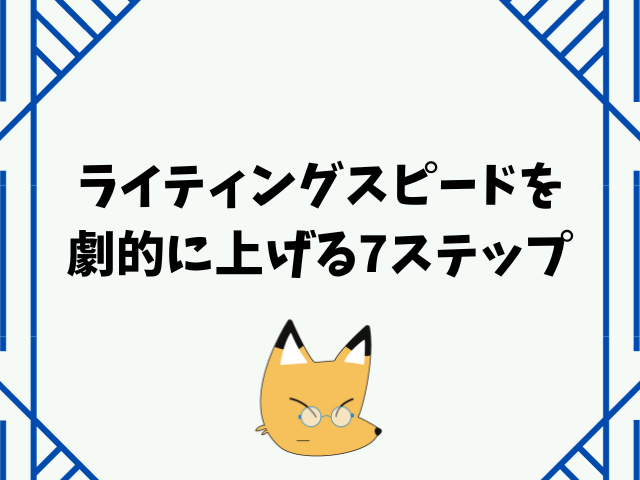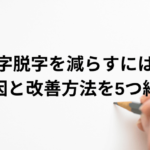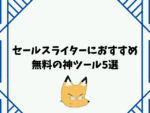どうも、狐乃文人です。
Webライターとして稼いでいくためには、ライティングのスピードを上げることも重要です。
SEOで上位をとれるような記事や売上アップが見込めるLPを速く書けるようになれば、Webライターとして稼ぎやすくなるでしょう。
そこで今回はライティングのスピードを上げる方法を解説します。
この記事を読むメリット
- ライティングスピードが上がらない理由がわかる
- ライティングスピードを上げる具体的な方法がわかる
ライティングスピードが上がらない原因
ライティングスピードを上げるために、まずライティングが遅い原因を理解しましょう。
以下はライティングスピードが上がらない主な原因です。
経験不足
ライターの経験が不足している場合、ライティングに時間がかかることがあります。
ライティングの経験が少ないと、ボキャブラリーの少なさや話の展開力の乏しさで悪戦苦闘することが多いでしょう。
特に「何を書いたら良いかわからない」と感じたら、ライターとしての経験不足の可能性が高いです。
事前の情報収集不足
ライティング前の情報収集が不足していると、文章を書く際に不安や迷いが生じ、スピードが遅くなります。
プロのライターでも、ライティングするテーマについて情報が不足しているとライティングスピードが遅くなります。
また、文字数、見出しの数、文章の使用目的など、ライティングの条件が定まっていない場合もライティングのスピードが上がらない原因です。
伝えることがまとまっていない
事前の情報収集と同じく、文章を通じて伝えたいメッセージ(主張)が決まっていないと、ライティングスピードが上がりません。
記事やLPなどの文章には、読者に伝えたいメッセージが込められています。
そのメッセージの内容が決まっていないと、アイデアがまとまらず途中で話が詰まってしまったり、読み返した時に何が伝えたいのかわからない文章になってしまいます。
構成が決まっていない
文章の構成が事前に決まっていないと、アイデアを整理することに時間がかかります。
大まかな話のあらすじを決めておかないと、書き直しの時間がかかってしまったり、話が脱線して文章が無駄に長くなってしまったり、ライティングスピードが上がらない原因となります。
タイピングミスが多い
タイピングミスの多さは、ライティングスピードの低下と大きく関係しています。
打ち間違いが多いほど修正に時間がかかり、全体的なタイムロスに繋がります。
何度も書き直していると感じたら、タイピングミスの可能性を疑いましょう。
タイピングが遅い人はこちらの記事が役立ちます。
▽
タイピングミスでお悩みなら、こちらの記事が参考になります。
▽
推敲に時間をかけすぎている
過度な文章の推敲(見直し)は、文章の完成を遅らせる原因です。
表現や読みやすさにこだわることは大事ですが、文章全体を書き終えていないのに何度も直していては、完成の目処がたちません。
ライティング時にずっと同じ箇所を書き直している、自分が納得するまで次の文章が書けないと自覚症状がある場合は注意してみましょう。
集中できる環境が整っていない
ライティングに集中する環境が整っていないことも、ライティングのスピードが遅くなる原因です。
集中できる場所、時間帯、道具など、環境を整えることもライターの役目の1つです。
なかなかライティングに集中できないとお悩みであれば、一度環境を整えるところから始めてみましょう。
ライティングスピードを上げる具体的な方法
ライティングスピードを上げる方法はさまざまありますが、効果的にスピードアップを狙うなら、複数の方法を併用した総合的なアプローチがオススメです。
ここからは、ライティングスピードを上げる具体的な方法を7つのステップに分けて詳しく解説します。
全てライティングの過程に沿って解説するので、ぜひステップ1から実践してみてくださいね。
集中できる環境を整える
ライティングスピードを高めたいなら、まずは集中できる環境づくりをしましょう。
下記のポイントを抑えることで、ライティングに集中できる環境に近づきます。
ライティングに集中できる環境作りのポイント
- 外部の騒音をほどよく遮断するために耳栓、もしくはイヤフォンをする
- スマホなど集中を妨げるものは椅子に座って手が届かないところに置く
- 参考にする本や資料は机の上に置いておく
- 長時間作業しやすくクッション性のある椅子に座る
- 作業時間を決めて、その時間は他のことをしない
こうした環境を整えることで作業に集中しやすくなり、ライティングスピードもアップします。
ライティングの工程を決める
ライティングをスピーディに行うには、作業手順を最初に決めておくことが重要です。
次にやることが明確になっていると集中力が持続しやすくなり、作業の効率もアップします。
また、「切りが良いところまで頑張ろう」「切りが良いからここで終わろう」といったs業のメリハリもつけやすくなります。
参考資料を集めて目を通す
ライティングのスピードを上げるなら、書く作業に入る前に参考資料を見ておきましょう。
書きながら情報収集をしていると、「資料を読む」「書く」の作業を交互にすることになり、ライティングスピードを低下させる原因になります。
最初にある程度情報をインプットした状態で書き始めることで、資料を読み返す時間を減らし、時短効果が期待できます。
文章で伝えたいことを明確にする
文章で伝えたいメッセージを予め明確にすることは、スピードを上げるうえで有効です。
書きながら考えていると、全文通した時に矛盾が生じたり、話が途中で脱線したりと読みづらい文章の原因にもなりかねません。
文章を書き始める前にメッセージを明確にしておくことで、文章で一貫した主張ができ、ライティングのスピードもアップします。
構成を考える
伝えたいメッセージが決まったら、次に文章全体の大まかな流れを考えます。
話の順番を決めておくとライティングスピードが上がるだけでなく、読者が読みやすい文章にもなります。
箇条書きでざっと走り書きしておくだけでも良いので、構成を考えることをおすすめします。
書きやすい見出しから書き始める
本文を書き始める時に、必ずしも冒頭から書く必要はありません。
プロのライターでも文章の冒頭は何度も書き直すぐらい難しいので、慣れないうちは書きやすいところからどんどん着手していきましょう。
書きやすいところから進めることで、時短効果もありますし、書き進めると筆も乗ってライティングスピードが上がる効果も期待できます。
文章の冒頭に悩んだら、こちらの記事をぜひ参考にしてください。
▽
PREP法を使って簡潔に書く
PREP法という文章のフォーマットを活用すると、ライティングスピードが更にアップします。
PREP法とは、Point (結論)、Reason (理由)、Example (例)、Point (結論) の頭文字を取った文章のフォーマットでそれぞれ下記の意味を含んでいます。
PREP法
Point (結論):簡潔に主張を述べる。
Reason (理由):その主張の理由を説明する。
Example (例):主張を裏付ける具体的な例を挙げる。
Point (結論):最後に再度主張をまとめる。
この方法を使うことで、論理的で簡潔な文章を迅速に書くことができます。
ちなみに、PREP法以外にも様々なフォーマットを活用すると、文章がわかりやすく簡潔にまとめられるようになります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▽
ツールで効率化をする
ライティングスピードをアップさせるにはライターのスキルアップだけでなく、機械を活用した効率化も重要です。
単純作業や面倒な作業は効率化することで、無駄な時間を短縮してライティングに集中しやすくなります。
ライターにおすすめな5つの神ツールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▽
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はライティングのスピードを上げる方法を解説しました。
ぜひ記事を参考に、ライティングのスピードをアップさせましょう!