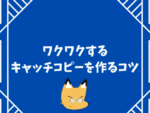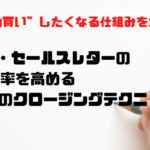どうも、狐乃文人です。
商品の魅力を伝えるためには、商品のスペックだけでなくメリットやベネフィットを伝えることも重要です。
メリットやベネフィットを伝えることで、お客さんの購買意欲を煽り、売上本数や成約率を伸ばしやすくなるでしょう。
しかし、メリットとベネフィットは非常によく似ているため、違いがわからないという人も多いかと思います。
そこでこの記事では、メリットとベネフィットの違いについて解説します。
この記事を読むメリット
- メリットとベネフィットの違いがわかる
- メリットとベネフィットの効果的な使い方がわかる
メリットとベネフィットの意味
マーケティングや広告の分野で、メリットとベネフィットはよく議論される概念です。
ここでは、メリットとベネフィットの違いを詳しく解説します。
メリットは客観的な利益
メリットは、商品やサービスを使ってユーザーが得られる客観的な利益を指します。
メリットに分類されるもの
- 商品の特徴:性能が優れている、機能が豊富など
- 商品の価値:商品単価、1個あたりの金額など
- 類似商品との違い:金額が安い、同じ金額も大容量など
- 数値やデータ:医学的根拠がある、使用者の90%以上が満足しているなど
メリットに挙げられるものは全て客観的事実がもとになっているため、全てのユーザーが商品を手にすることで得られる利益とも言えますね。
ベネフィットは主観的な利益
ベネフィットは、商品やサービスを使ってユーザーが得られる主観的な利益を指します。
ベネフィットに分類されるもの
- 優越感:「数量限定品をGETできて嬉しい」など
- 安心感:「有名人の〇〇さんと同じものが買えて嬉しい」など
- 充足感:「自分の悩みを解消できた」など
- 承認欲求:「友達に褒められて嬉しい」など
ベネフィットに挙げられるものはユーザーの感情に左右されるため、個人差が出やすく全てのユーザーが同じ利益を得られません。
メリットとベネフィットの例
ここからは具体例を用いて、メリットとベネフィットの違いを解説していきます。
具体例からメリットとベネフィットの違いをより深く理解できるでしょう。
例1:自動車
自動車の場合、下記のようなメリット、ベネフィットが考えられます。
メリット
- EV車なので環境に優しい
- 車内が広くたくさん荷物を運べる
- 高性能なアシスト運転機能がついている
ベネフィット
- すれ違う車や人から注目を浴びて承認欲求が満たされる
- 友人に自慢できる
- 世界有数の限定モデルの車に乗っている優越感に浸れる
このように車の性能と車に乗っている人の感情を分けて考えることで、メリットとベネフィットの違いがわかりやすくなります。
例2:ダイエット食品
次にダイエット食品を例にメリット、ベネフィットの違いを考えてみましょう。
メリット
- おいしいのに低カロリー
- リーズナブルなお値段
- 味が豊富
ベネフィット
- 食事がおいしいからダイエットを楽しめる
- 続けることで理想の体型が手に入る
- モデルの〇〇さんみたいになりたいから同じものを食べたい
先にメリットを書き出してからベネフィットを考えると、スムーズに出てきますよ。
メリットとベネフィットの使い分け
メリットとベネフィットを使い分けることで、効果的に商品の魅力を伝えることができます。
そこでここからは、場面別でメリットとベネフィットの使い方をご紹介します。
集客ではベネフィット使う
広告やLPなど、集客の場面ではベネフィットが有効です。
キャッチコピーでどのような体験、感情が提供できるかをイメージさせることで、見込み顧客の関心を引き付けます。
具体的に見込み顧客が「なぜそれを手に入れる必要があるのか?手に入れたらどんな体験、感情になるか?」を伝えましょう。
魅力的なキャッチコピーの作り方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▽
商品の紹介ではメリットを使う
商品やサービスの特徴を伝える際には、その特徴がどのような価値を持つかを示すことが大切です。
そのため、この場面では商品のメリットを伝えましょう。
技術的な情報や機能に興味を持つ顧客にメリットを重点的に伝えることで、他社の類似商品との差別化が図れます。
クロージングではベネフィットを使う
購買の最終段階であるクロージングの場面では、最後のひと押しとして改めてベネフィットを伝えましょう。
商品を手に入れることで顧客がどのような体験や感情が得られるのかを再度伝えることで、購買意欲を高め購入の決断を後押しできます。
顧客が商品やサービスの提供する価値を実感できるように、ベネフィットを具体的に描写しましょう。
この他にもクロージングの効果を高めるテクニックはたくさんあります。
さらに効果的なクロージング方法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▽
まとめ
メリットとベネフィットの違いを理解し、適切に使い分けることで効果的に商品の魅力を伝えることができます。
ぜひこの記事で紹介したメリットとベネフィットの違いを参考に、魅力が伝わりやすいライティングをしていきましょう。